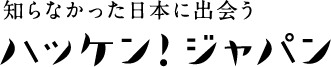撮影/中島光行
天保9(1838)年創業、錫(すず)製品をつくり続けている工房「清課堂」。古くは道具筋だった寺町通、京都市役所のすぐ近くにその店はあります。当代主人の山中純平さんで七代目を数え、いまや錫だけにこだわらず銀や銅など各種金属素材を用いた日用品としての金工品も数多く提案しています。
錫工芸の歴史は古く、古代エジプト王朝の遺跡に出土例があるほど。日本では、飛鳥・奈良時代に中国から渡来したと伝えられ、当初は社寺の道具や貴族・武士階級の酒器および茶器に重用されました。
京の錫製品が長らく愛されてきたのは、公家文化の影響が強いと考えられます。そんな高級品が一般的に広まった江戸時代に初代 山中源兵衛が現在の場所に工房を構えてから。今日まで、宮中の御用品・神社仏閣の荘厳品・煎茶道の各御家元お好みを手掛けてきましたが、現在、甁子(へいし)や高杯(たかつき)といった錫製の神仏具を製作しているのは、国内では清課堂と他1軒を残すのみとなりました。

錫の最大の特長は、その柔らかさ。 金属とは思えないしっとりと吸い付くような手触りが、錫ならではの持ち味といえます。手で曲げられるほど柔らかいため加工しやすいと同時に、傷つきやすく、長く使い続けるなかで傷や凹みが生じ、色合いにも深みが増していく――その経年変化こそ、錫の器を愛でる醍醐味なのです。使い込むほどに手に馴染む、その風合いと佇まいは、移ろう様に感じ入る「侘び寂び」(わびさび)にも通ずるものがあります。
また、錫の酒器を使うとお酒の味がまろやかになるとも良く耳にします。これは、錫が持つ独特の香りゆえ。加えて、錫は酸化や腐食にも強く、熱伝導性と除菌効果に優れた性質から、食器として重宝する素材なのです。

錫製品のつくり方は、大きく分けてふたつ。 ひとつは、溶かして鋳型に流し込み、固まった錫をろくろと鉋を使って削る「鋳造」。もうひとつは、板状にした錫を鳥口にあてて金鎚で叩いて成形する「鍛造」です。
材料が柔らかいからこそ、仕上げの研磨は職人の手加減が頼り。緻密かつ正確な技術が求められるため、使う道具の多くも自ら作製するというから驚きです。

元は鍛冶屋に頼んでいた工具の「鳥口」(とりぐち)や「当て金」も、近年ではつくる職人がどんどん減っていき、「もう自作するしかなくなって仕方なく、ですよ(苦笑) 山から樫の木を探し出してきて削ったり、金鎚の頭をザラザラするように手を加えたり。これらの道具は消耗品なので、50年後、100年後を見据えてストックしています」と、山中さん。
そうして目指すは、シンプルで端正なカタチ。華やかな装飾は必要ない。静かな、だが力強い存在感を放つ、品格あるものづくり。
光を受けて違いを見せる肌合い、使い込むほどに愛着が増す温もり、小さな傷ひとつに想い出が過る贅沢さ。丁寧につくられたものを長く使い続けることの大切さを伝えるため、新しいものをつくり出すことに留まらず、他店の製品であっても修理を受ける姿勢もまた、幾世代もの先を見据えた清課堂の流儀。
「金属それぞれに得手不得手があり、お客様にとって使いやすい美しいカタチを追求していくことが大事。アルミニウムに取って変わられてもいい、竹などの金属以外のものでもいい。材料の一歩先に工芸の意義があると考えています」
例えば、徳利ひとつとってみても、重心、直線と曲線、高さ、口の大きさ、重さ、テーブルとの調和、他の器との調和……といったもの全てを考慮してこその「バランス感覚が美しさに繋がる」と山中さんは言います。
「削りすぎては戻れませんから、力加減が何より肝心。縁の造作だけ見ても、角が大事なんです。野暮ったくならず、でも尖りすぎず。それこそが職人の技の見せ所」
お気に入りの器を日常使いすることのささやかな悦び、心惹かれる器を少しずつ集める幸せへの提案が、ここにはあります。
「伝統の美」あってこそ磨かれる「現代の美」の有り様を、ぜひ手に取って確かめてみてください。

撮影/中島光行 https://hakken-japan.com/columns/nakajimamitsuyuki/
清課堂
京都市中京区寺町通二条下ル妙満寺前町462
TEL 075-231-3661
https://www.seikado.jp/
【おすすめ記事】