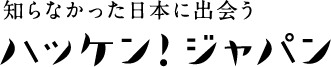2024年3月、上野・東京国立博物館内「九条館」で着物専門店「きものやまと」による米沢さんち染織の特別展が先行開催された。そして4月18日(木)からは、東京会場を皮切りに全国8会場を巡る「古今 いろいろ」展がスタートする。
なぜ、いま米沢織なのか。その理由は、他のエリアでは見られないようなバラエティに富んだものづくりの独自性にあるという。きものやまと広報の山井茜さんに「米沢さんち」に寄せる想いをうかがった。

「米沢さんち」が持つ、驚くほどの多様性
米沢は、東京駅から山形新幹線で2時間ちょっと。米沢牛や果物などのグルメ、周辺の歴史や自然を楽しむ観光スポットとして人気だが、冬は雪深く、かつては陸の孤島と呼ばれた。米沢の織物、「米沢織」という言葉を聞いたことがあったとしても、それが一体どんなものか、着物に詳しい人以外には知られていないといっていいだろう。
やまと広報の山井さんに、今回の企画展で米沢をクローズアップした理由を尋ねると
「米沢織は非常にユニークな歴史をもち、唯一無二の魅力を築き上げています。そのことがなかなか広まっていないように感じ、だからこそ今回もっと多くの方に知っていただきたいと思いました」
という答えが返ってきた。
「米沢の織物産業は、江戸時代に上杉鷹山(ようざん)公によって生まれ、現在まで続いてきました。草木染など天然染料を用いる人、モール糸やウール糸を使う人、絣(かすり)のつむぎを作る人、250年以上の歴史がありながらも今も新たな糸づかいへチャレンジを続ける機屋(はたや)など。一つのエリア内で、驚くほどたくさんの技法が見られます。そうした多様なものづくりが、鷹山公の存在感によって一つにまとまっているように感じられるのです」

いまも脈々と息づく上杉鷹山公の教え
上杉鷹山公もまた、歴史に詳しい人以外は知らないかもしれない。戦国ヒーローのひとり上杉謙信の末裔、米沢上杉家九代目。アメリカ大統領ジョン・F・ケネディが尊敬する歴史上の偉人として鷹山公の名前を挙げ、「為せば成る 為さねば成らぬ何事も 成らぬは人の為さぬなりけり」、この言葉なら知っている、という人も多いだろう。
3月の展示会場となった九条館に作り手として米沢から来られていた「近賢織物」の近藤哲夫さんは、1860年創業の老舗を継ぐ五代目。「鷹山公の顔は米沢市内の小・中学校の体育館に肖像画が飾られているから、米沢では知らない人はいない」と笑う。
鷹山公は、江戸時代の「天明の大飢饉」の頃、米沢藩の財政再建を成し遂げた名君。上杉家始祖の地である越後から麻織物と縮(ちぢみ)織の職人を招き、米沢の特産物に育てた。技術の流出をよくは思わない越後との間でさまざまな困難に見舞われたという。そこで発揮されたのが、敵に塩を送った逸話で有名な謙信公から受け継がれた上杉家の精神だ。
「たとえば博多織なら献上帯とか、織物産地には看板となる商品や技術があります。米沢織物はどうかというと、ひとつにイメージを絞れないほどバラエティ豊か。このような発展の仕方には、各自がよその産地に学び、そこで生まれたものを尊重して、それとは違うオリジナルをつくろうと工夫して棲み分けをしていった。こんなところにも鷹山公の教えが息づいていると思います」(近藤さん)

外からの技術を取り入れ、独自の発展
展示された織物の中で目を引いたのが、カラフルに染色された綿状の物体。糸になる前の繊維だそうで、ウールの染色でよく行われる「トップ染め」という技法を参考に開発された、ユニークな先染めの織物になるという。
通常、着物の生地は糸から反物にしてから染めるのが主流。これに対し「トップ染め」は、綿状の繊維の段階で草木染めを施してから糸を作り、その糸で反物を織る。溶けるようになめらかなグラデーションに仕上がり、見た目にも美しい。この技法自体が、まるで希少な野草の花のように、雪深い米沢の地でひっそりと存在してきたことも興味深い。
普通なら特許を取るべき技術だろうと思うが、米沢では周囲の同業者間でオープンに共有という話にも驚いた。
「たしかに、米沢の職人は商売気があまりない。有名な着物の産地は、献上するための着物や帯をつくってきたところが多いのですが、米沢では糸や反物の状態で出荷して収入を稼いでいた歴史がある。そのため手間隙のかかる独自技法が生き残ったかもしれませんね」という職人さんのお話も印象的だった。

織物が「世に出る」ことの奇跡、そのための伝承
商売気がないからこそ昔ながらの技法が共有されて残ったが、それでも職人が一人欠ければ世に出ない、そういう原案は山のようにあるという、
たとえば、着物の帯などに使われるジャガード織。図柄を織るための型紙「紋紙」をつくる職人や、その紋紙をもとに機織りをする職人がいなければ完成しない。熟練した紋紙職人は、穴の配置を見ただけで大体どのような柄になるのかわかるが、同じジャガード織に携わっていても機織りの職人は、紋紙を見ただけでは柄の判別はつかないという。
同様に絣(かすり)の着物なら、柄の下絵を描く職人、図案をもとに糸を染色するための「糸準備」をする職人、染色職人など、それぞれの過程で専門の職人が必要で、それぞれの分野について独自の技術が代々にわたって伝承されてきた。
工芸の分野で問題になるのが、後継者をどう育てるか。近賢織物の近藤さんに、次の代はどうなるのか聞くと、「継ぐか?じゃない。息子には継げ!と言っています」と即答。「ただし、社会に出て、飯も食えるようになってから。ただのバカボンじゃ困る(笑)」。長年使用するうちに摩耗する紋紙はトラブルに備えてデータ化するなど、IT導入にも取り組んでいる。
展示会場内で流れる動画でも、「十一代目と子供の頃から言われて育ちました」という1770年創業の織元「白根澤」当主の言葉が印象的。他の工房でも若い職人が次々に育っているそうだ。

伝統を守ると同時に、新たな分野への挑戦も
米沢織物は歴史的に麻から始まったが、そこだけに固執せず絹も積極的に取り入れ、縦糸に絹で横糸に麻を使った織物などもつくっている。また着物だけでなく洋服の生地にも早い段階から対応し、いまでは世界のトップブランドでも採用される品質になった。
「みんなが驚く、新しいものを生み出していきたい」と話す近藤さん。老舗の伝統を守りながらも、慣習にとらわれず新しいものづくりに挑戦している。洋服に使われるモール糸で帯地を織るなど、素材の新しい可能性を探すだけでなく、逆に明治時代の見本帳から新たな発見や着想を得ることもあるという。
伝統を受け継ぐ覚悟と、新しい技術を取り入れて独自の産物として発展させる柔軟な姿勢。その絶妙なバランス感覚が米沢織物の特色でもある多様性を育んできたのだと思う。
美しく多彩な米沢織物の数々を見ると、それが世に出た奇跡と希少性が納得できるが、骨董品や歴史的資料として美術館に飾られるためのものではない。実際に着る人がいなくなれば、伝統技法も途絶えてしまう。
着物専門店やまとの山井さんは
「着物好きはもちろん、それ以外の方にも米沢織物のユニークさを知っていただきたい。私たちも着物をつくって売るだけでなく、さんちのこと、背景となる技術や文化を伝えることによって関心をもつ方が増えて、それが着物の未来にもつながってほしい」と話す。

着物を骨董品にしない、伝え手としての責任
全国各地に店舗展開する「きものやまと」は、近年めざましく変わってきた印象がある。店頭に立つスタッフも、毎シーズン季節を先取りして打ち出される商品企画にも、思い切りの良い若々しさが目立つ。着物が日常の衣服ではなくなってから生まれ育ち、それでも着物が好きで、着物の良さを伝えようと奮闘する人たちがいる。
店頭でのワンコイン着付け教室、結ばないワンタッチ帯の加工サービスを手軽な価格で提供など、着たいのに「着られないをゼロにする」そのための努力が続いている。
きものやまとがプロデュースする米沢さんち染織展は、4月18日(木)神田明神ホールからスタート。会場内では、多種多様な米沢の織物の販売会と山形ならではの紅花染めの体験、機(はた)織の実演などが行われるほか、米沢銘菓の販売コーナーも。山形県産フルーツを使って作られたミニジャムのおみやげプレゼントもある。
かつては陸の孤島と呼ばれ、冬は雪深く、だからこそ今日まで大切に守られ育まれてきた米沢の織物。独自性と多様性が生み出す豊かな広がりを、この機会にぜひ体感してほしい。

【INFORMATION】
米沢さんち染織展「古今 いろいろ」
東京・大宮・仙台・札幌・大阪・岡山・熊本・鹿児島の8会場で順次開催 ※終了
入場無料。各会場の日程と詳細、来場予約は公式サイトより
https://www.kimono-yamato.co.jp/sale/yonezawa_sanchi_kokoniroiro2024/
【おすすめ記事】
山形の紅~花嫁と母をつなぐ思い出の品に受け継がれる紅の物語
着物コラム「恋する日本の伝統色」シリーズ(辻ヒロミ)